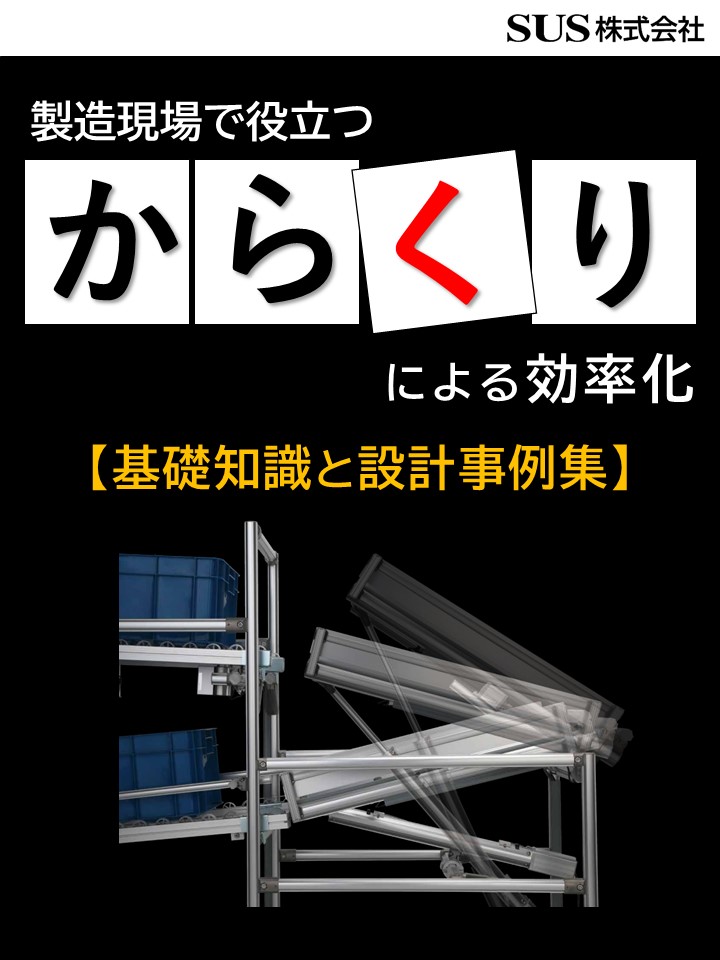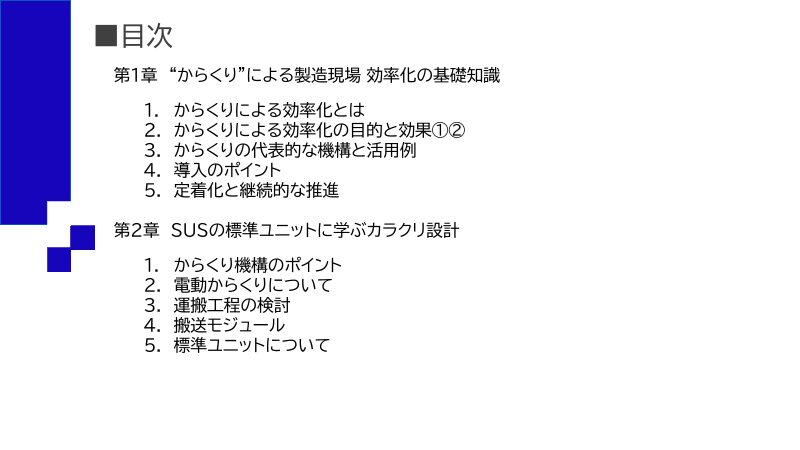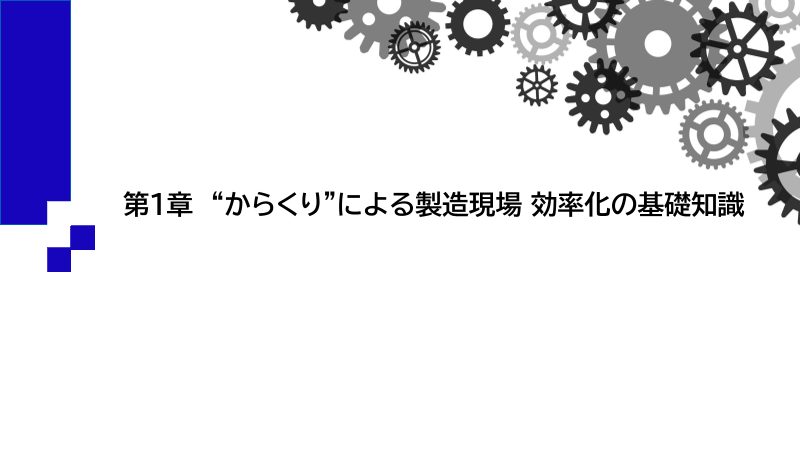1/16ページ
ダウンロード(1.5Mb)
製造現場の課題解決に役立つ「からくり」機構の基礎や活用事例ををわかりやすく解説
本資料は、製造現場の作業効率アップやコスト削減を目指す方に向けて、「からくり」機構の基本から活用事例までを分かりやすくご紹介しています。重いものを持ち上げる、部品を自動で戻すなど、重力やてこ、バネなど身近な原理を活用し、現場の課題を手軽に解決する方法を解説しています。これにより、現場改善の機構や装置を保有している資材や端材を活用して、コストを抑えながら効率化を実現できる点が大きな特長です。
また、実際の現場で役立つ代表的な機構例や、導入・定着のポイント、従業員のやる気を高める仕組み作りについても触れています。
さらに、SUSの標準ユニットを使った搬送装置の設計ノウハウや、電動モジュールとの組み合わせによる安定搬送の工夫など、現場で今すぐ役立つ情報が満載です。初めての方にも理解しやすい内容となっていますので、ぜひご活用ください
このカタログについて
| ドキュメント名 | からくりによる効率化の基礎知識と設計事例集~現場で役立つ知恵と工夫で生産性・安全性を向上~ |
|---|---|
| ドキュメント種別 | ホワイトペーパー |
| ファイルサイズ | 1.5Mb |
| 登録カテゴリ | |
| 取り扱い企業 | SUS株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ

このカタログの内容
Page1
からくりによる効率化の基礎知識と設計事例集
~現場で役立つ知恵と工夫で生産性・安全性を向上~
Page2
■目次
第1章 “からくり”による製造現場 効率化の基礎知識
1. からくりによる効率化とは
2. からくりによる効率化の目的と効果①②
3. からくりの代表的な機構と活用例
4. 導入のポイント
5. 定着化と継続的な推進
第2章 SUSの標準ユニットに学ぶカラクリ設計
1. からくり機構のポイント
2. 電動からくりについて
3. 運搬工程の検討
4. 搬送モジュール
5. 標準ユニットについて
Page3
第1章 “からくり”による製造現場 効率化の基礎知識
Page4
1-1.からくりによる効率化とは
からくりによる効率化とは、製造現場や作業現場における困りごとや課題を、現場で働く人
たち自身が知恵と工夫を凝らし、重力やてこ、バネなどのシンプルな物理原理や、歯車、カム、
滑車などの簡単な機構を活用して、ローコストかつ省エネルギーで解決する改善活動です。
複雑な電子制御を極力使わず、現場にある資材や端材も積極的に利用し、手作りで装置や
仕組みを構築する点が特徴です。
この「からくり」という言葉は、日本の伝統的なからくり人形に由来し、複雑な動きをシンプ
ルな仕組みで実現する発想が現代の生産現場にも応用されています。
Page5
1-2.からくりによる効率化の目的と効果①
目的 1 効果 1
1現場で発生する課題(重筋作業、不自 作業時間短縮や動線改善、ミス減少で
然な姿勢、無駄な動き、危険作業など) 生産性を向上させる
を現場の知恵と工夫で解決する
目的 2 効果 2
2シンプルな物理原理や簡単な機構を使 設備投資や材料費の抑制、修繕費削減
い、ローコスト・省エネで改善を進める でコストダウンを実現する
Page6
1-2.からくりによる効率化の目的と効果②
目的 3 効果 3
3現場改善の機構や装置を保有している 資源を有効活用し、廃棄物の発生を抑
資材や端材を活用する えることで、環境負荷の低減が促進さ
れる
目的 4 効果 4
4従業員が自ら考え効果を実感すること 従業員のモチベーションが向上し、現場
で現場力や人材育成を企図する が活性化する
Page7
1-3.からくりの代表的な機構と活用例
機構・原理 活用例
重 力 傾斜をつけたレールで部品を自重で滑り降ろし、手作業による運搬を不要にする
て こ レバーアームで重い蓋や部材を少ない力で持ち上げられる
バ ネ コイルスプリングを使い、部品を自動的に元の位置に戻すリターン機構
滑車・輪軸 上下移動を補助し、作業者の負担を減らす
カム・歯車 回転運動を直線運動や往復運動に変換する等、さまざまな動作を実現する
ゼネバストップ 部品を一つずつ正確に送り出し、取り違えや詰まりの発生を抑止する
ベルト・チェーン 軸間の距離が長い場合の力の伝達に適しており、ベルトコンベアなど搬送にも活用
Page8
1-4.導入のポイント
管理者視点 現場作業者視点
現場観察と課題抽出 作業効率化と無駄削減のアイデア検討
• 実際の作業現場を観察し、作業者の動きや作 • 日々の作業の中で、現場で感じる負担や課題
業手順、課題を洗い出す を自ら見つけ出す
例)どうすれば自分たちの作業がよりラクで
安全になるか 等
現場従業員の意見収集
• 現場の知恵を活かした工夫やアイデアを改善
• 現場の声をヒアリングし、具体的な困りごとや 策として提案する
改善アイデアを集める
試作と検証
• 試作品を作り、現場で実際に使いながら効果
を検証する
継続的な改善活動
• 一度作ったら終わりではなく、現場の声を反
映しながら改善を継続する
Page9
1-5.定着化と継続的な推進
からくりによる効率化を現場に根付かせ、継続的に発展させていくためには、単発の取り組み
で終わらせず、企業文化や日常業務の一部として定着させることが重要です。
① 成功事例の共有
現場で実施したからくりによる効率化の事例や成果を社内で積極的に共有し、他部署や他ライン
への波及を促進する。
② 表彰・評価制度の導入
優れた活動やアイデアに対して評価や表彰を行い、従業員のモチベーション向上と改善活動の活
性化を図る。
③ 継続的な教育・研修
新入社員や若手社員向けにからくりによる効率化の基礎や実践ノウハウを学ぶ機会を設け、現
場力の底上げを目指す。
④ 改善提案制度の活用
従業員が日常的に気づいた点やアイデアを提案できる仕組みを整え、小さな工夫でも現場改善
につなげる。また、一度製作したからくりも、随時、改良を加えていくことも重要。
Page10
第2章 SUSの標準ユニットに学ぶカラクリ設計
Page11
2-1.からくり機構のポイント
当社は、お客さまの工場で発生するさまざまな問題を解決するために、装置の設計から製作、納品までを行っています。
これまで多くの実績を積み重ねてきた中で、「からくり機構」を使った装置も数多く手がけてきました。
からくり機構は、複雑な制御が不要なため省エネでメンテナンスもしやすく、現場の効率化や品質向上に貢献しています。
一方で、注意しなければならないポイントもあります。たとえば、同じ搬送ラインで重さの異なるワークを扱う場合、軽いワークは途
中で止まる「チョコ停」が発生するリスクがあり、重いワークは勢いがつきすぎてワーク自体に傷がついたり、装置に負担がかかった
りするリスクがあります。こうした課題は搬送の安定性や品質に影響を及ぼすため、最適な設計が求められます。
異なる条件のワークを一つの装置で安定して搬送するには、単にからくり機構を設計するだけでは機能しない場合があり、設計者
の経験や試作が欠かせません。からくり機構は有用ですが、多様なニーズに応えるにはさらなる工夫が必要です。当社が長年取り
組んで得た解決のヒントを次ページより解説します。
Page12
2-2.電動からくりについて
右図はチョコ停の代表的な解決方法を示しています。
安定してワークを搬送するためには、適切な
「対策1」および「対策2」の方法ではチョコ停自体は解
傾斜角を設定する必要があります。小さい
消できますが、重いワークの場合、衝撃が大きくなり、 傾斜ですと前に進もうとする力が弱く、抵抗
のばらつきによって止まってしまうことがあ
根本的な解決には至りません。 ります。一般的にはコロコンは3°~5°に設
そこで注目していただきたいのが「対策3」です。 定するとよいといわれています。
当社では“からくり”と“電動”を融合した搬送装置を
進もうとする力より抵抗が大きい場合、もの
「電動からくり」と位置づけ、積極的に推進しています。
を動かすことができません。スムーズに安定
して搬送するためには抵抗値の低いパーツ
“からくり”と“電動”それぞれの特長を活かし、適材適 が有効です。ベアリングを組み込んだベアリ
所で使い分けることで、汎用性が高く、かつローコス ングコロコンは抵抗が小さく、安定搬送に適
しています。
トな搬送装置のご提供を実現しています。
電気制御に対して抵抗感がある方も、当社の電動 GFコンベアなど、電動モジュールを使用す
ることで、安定搬送が可能です。ワークの重
パーツや、“SiO”(エスアイオー)による簡単プログラ
量差や、コンテナBOXの変形などの影響を
ミングをご利用いただくことで、その手軽さを実感し 受けることがない上、速度調整や動作制御、
上昇する動きの実現など、電力を使用しな
ていただけます。
いからくりでは不可能な、さらに発展した搬
送にも対応します。
Page13
2-3.運搬工程の検討
このページでは、当社が搬送装置を設計する際の検討プロセスについてご紹介します。
まず「何を運ぶか」(ワークの大きさ・重さ・形状など)を確認し、次に「どう運ぶか」(搬送ルート、距離、投入・排出方法など)を確認します。
これらを整理し、具体的な仕様に反映していきます。
ワーク軽→チョコ停→傾斜急or電動アシスト 搬送距離長い→終点高さ低くなる→昇降 積まれたワークを1体ずつにして搬送→段バラシ
ワークを積んで搬送→段積み
ワーク重→スピード・衝撃→緩衝or減速 搬送先が直線状にない→水平ターン・90°ターン 通路をまたいで搬送する→空中搬送
柱
ワーク重+多→強度計算(たわみ)→柱追加or補強 次工程へワーク供給→ワーク1体ずつ供給→切出し ワーク供給先が別ラインで距離が長い
→空箱を回収して戻る→AGV台車+ストックシューター
ワーク形状安定 搬送ライン上で作業が行われる→水平搬送
→低い(段ボールなど)→搬送安定しない→幅広コロコン
→高い(プラコンテナなど)→搬送安定する→幅狭コロコン
Page14
2-4.搬送モジュール
当社では「動きの基本単位」を搬送モジュールと定義しています。
たとえば、持ち上げる・運ぶ・回すなどの動作ごとに搬送モジュールがあります。
前項で決定した仕様に基づき、様々な搬送モジュールを組み合わせることで、最終的な搬送装置を構成します。
水平搬送 傾斜搬送 折り返し 昇降 切り出し
乗り移り(送り出し、引込み) 減速 水平ターン 90°ターン 段バラシ
段積み 空中搬送 ストック
Page15
2-5.標準ユニットについて
当社では、搬送モジュールをパッケージ化したものを「標準ユニット」と定義しています。現在、7種類の標準ユニットを取り揃えており、
今後もバリエーションの拡充を計画しています。
また、各標準ユニットは、サイズを変更してご購入いただくことも可能です。
折り返しシューター(からくりタイプ) エレベーターシューター(からくりタイプ) 水平ターンシューター(からくりタイプ) 水平搬送シューター(電動タイプ)
折り返しシューター(電動タイプ) エレベーターシューター(電動タイプ) 水平ターンシューター(電動タイプ)
H
D
W
標準ユニットに使われているコンテナ
W:335mm D:503mm H:149mm
空箱 1.3kg おもりを中へ入れて実箱としています。
Page16
製品・サービスに関するお問い合わせ、カタログ・資料請求については
こちらのページでご案内しています